この記事のポイント
・専業主婦でも、事故による休業損害や慰謝料などを請求できる可能性がある
・慰謝料の金額は収入ではなく、ケガの程度や治療期間などで画一的に決まる
・弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる(上限あり)
専業主婦であるYさんは、買い物のため自動車を運転中に追突事故にあい、右足を骨折するケガを負ってしまいました。ケガのため半年ほど家事ができなくなり、家族の生活にも多大な支障が生じました。
会社員時代、同僚が交通事故にあいさまざまな賠償を受けていたことを思い出したYさんは、専業主婦で決まった収入のない自分は賠償金を減らされてしまうのではないか心配です。
この記事では、専業主婦(夫)が交通事故の被害にあった場合の、
- 加害者に請求できる賠償金の種類
- 加害者に請求できる慰謝料の計算方法
- 慰謝料の額を増額するポイント
について、弁護士が解説します。
無収入の専業主婦(夫)が追突事故の被害にあった時に慰謝料はもらえる?
交通事故にあったとき、被害者は加害者に対し、事故により生じた財産的損害と精神的損害について賠償金を請求できます。
財産的損害とは、ケガの治療にかかった治療費や仕事を休んだことによる休業損害などをいいます。
精神的損害とは、ケガなどにより被った精神的苦痛をいい、これについては
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
を請求できます(それぞれの内容については後で述べます)。
専業主婦(夫)で無収入であることにより、慰謝料が少なく見積もられてしまうのではないかと心配になるかもしれません。しかし、慰謝料は財産的損害ではなく精神的損害(=痛い・つらいといった苦痛)に対する賠償金なので、金額の算出にあたり、被害者に収入があるかどうかは関係ありません。
これに対し、慰謝料以外に請求できる賠償金の中には、それを算出する際に被害者の収入が影響するものもあります。
専業主婦が追突事故にあった時に請求できる示談金
上で述べたように、交通事故にあった被害者が加害者に請求できる示談金(賠償金)には、財産的損害に対するものと精神的損害に対するもの(慰謝料)があります。
財産的損害のうち、休業損害や逸失利益については、被害者の収入額に応じて算出されるため、被害者の収入の有無が金額に影響します。
以下、交通事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金の種類を見てみましょう。
(1)慰謝料
事故により生じた精神的損害(=痛い・つらいといった苦痛)に対する賠償金です。入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。
後で述べるように、これらの慰謝料の額は、事故時における被害者の収入の有無や収入額にかかわらず、一律に定められた計算式を用いて算出します。
(2)治療費
入院費や診療費、検査費、手術費用、処方箋料など、治療にかかった費用です。実際に負担した実費を請求することになるため、領収証を保管しておく必要があります。
(3)通院交通費
医療機関に通院するために要した交通費です。電車やバスなどの公共交通機関の運賃、自家用車のガソリン代、タクシー代など、実際にかかった実費を請求できます。
(4)休業損害
交通事故によるケガで休業し、得られなくなった(または減ってしまった)収入です。
休業損害の額は、事故直前の収入から算出した1日あたりの基礎収入額に、休業した日数をかけて計算します。
基礎収入額は事故直前の収入額から算出するため、収入のない専業主婦(夫)は請求できないかというと、そうではありません。
専業主婦(夫)の場合は、基礎収入額は厚生労働省が毎年発表する賃金構造基本統計調査(賃金センサス)を用いて算出されます。つまり、実際は無収入であっても、計算上は女性の平均額程度の収入があるものとして扱われます。
ちなみに、2019年度の専業主婦(夫)の1日あたりの基礎収入額は1万630円とされています。
なお、就業もしている兼業主婦(夫)の場合は、賃金センサスから算出した額と就労により得ている収入を比較して、多い方の基礎収入日額が用いられます。
(5)逸失利益
逸失利益とは、事故にあったことにより得られなくなった将来の収入をいいます。
- 後遺障害逸失利益(事故により後遺障害を負った場合)と、
- 死亡逸失利益(事故により死亡した場合)
の2種類があります。
このうち、後遺障害逸失利益は
基礎収入日額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
で算出されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに定められており、例えば、むち打ち症で後遺障害12級が認定された場合の労働能力喪失率は、14%とされています(つまり、100%のうち、14%が失われた状態)。
「ライプニッツ係数」とは、利息などを控除するための数値です。
専業主婦(夫)の場合の基礎収入日額の算出方法は、4の休業損害の場合と同じです。
つまり、専業主婦(夫)の場合、基礎収入日額は賃金センサスを用いて算出されます。
また、就労もしている兼業主婦(夫)の場合、賃金センサスにより算出された額と実際の収入の多い方を基礎収入日額とするのも休業損害と同様です。
(6)修理費
交通事故で破損し、修理が必要になった車両を直すためにかかった費用です。
(7)その他
被害者に対する付添看護費・装具費(コルセット・関節用装具・サポーターなど)・雑費・葬祭費などです。
専業主婦が追突事故にあった時の慰謝料の計算方法
以上のように、休業損害と逸失利益については、その金額を算出するにあたり被害者の事故時における収入額が影響します。専業主婦(夫)に場合は決まった収入がないため、賃金センサスから基礎収入額を決定します。
これに対し、治療費や通院交通費・修理費などは、実際にかかった費用を請求することになるため、事故時における被害者の収入は影響しません。
慰謝料についても、事故時における被害者の収入は影響しません。
では、慰謝料については金額をどのように算出するのでしょうか。
以下では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の計算方法について説明します。
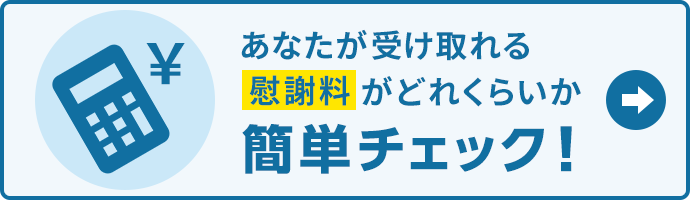
(1)慰謝料を算出する基準は3つある
前提として、慰謝料の額を算出する際の基準には、
- 自賠責の基準
- 任意保険の基準
- 弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)
の3つがあります。
3つの基準の具体的な内容は次のとおりです。
(1-1)自賠責の基準
自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
(1-2)任意保険の基準
各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責基準以上ではありますが、弁護士基準と比べると、かなり低く設定されています。
(1-3)弁護士の基準(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもので、通常、弁護士が交渉や裁判をするときに使う基準です。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、多くの事案で、
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。
以下では、3つの慰謝料額の計算方法を、自賠責の基準と弁護士の基準を比較しながら説明します。
(2)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故でケガを負ったことに対する慰謝料です。傷害慰謝料ともいいます。
入通院の際にかかった治療費や交通費とは別に請求可能です。
入通院慰謝料は、治療期間や実際に入通院した日数に基づいて計算します。基本的に、入通院期間が長くなるほど高額になります。
入通院慰謝料の目安について、自賠責基準により算出した場合と弁護士基準により算出した場合を比べると、一般的には次の表のようになります。
【入通院慰謝料の目安(自賠責基準と弁護士基準の比較)】
| 通院期間 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 (自覚症状のみ) | 弁護士の基準 (他覚症状あり) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
| 2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
| 3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 | 73万円 |
| 4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 | 90万円 |
| 5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 | 105万円 |
| 6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
※自賠責の基準については、2020年4月1日以後に発生した事故の場合の金額です。
※自賠責の基準については、ひと月の通院日数が15日以上の場合の金額です。
※「弁護士の基準(他覚症状あり)」とは、自覚症状だけでなく他覚症状(レントゲンやCT検査などによる異常)も認められる場合を指します。
このように、一般的には弁護士の基準のほうが高額になることが分かります。
(3)後遺障害慰謝料
交通事故で受けたケガが完治せず、後遺症が残った場合に発生する慰謝料です。
後遺症が、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により「後遺障害」として認定されると請求できます。
後遺障害には、症状の部位や重さに応じて1~14級(および要介護1級・2級)の等級があり、どの等級に認定されるかによって慰謝料の金額が変わってきます(最も重い1級が最も金額が高くなります)。
後遺障害慰謝料は、1の入通院慰謝料とは別に請求が可能です。
後遺障害慰謝料の目安について、自賠責の基準により算出した場合と弁護士の基準により算出した場合を比べると、一般的には次の表のようになります。
【後遺障害慰謝料の目安(自賠責の基準と弁護士の基準の比較)】
| 後遺障害等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |
|---|---|---|
| 要介護1級 | 1650万円 | 2800万円 |
| 要介護2級 | 1203万円 | 2370万円 |
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責の基準については、2020年4月1日以後に発生した事故の場合の金額です。
このように、後遺障害慰謝料の相場についても、一般的には自賠責の基準より弁護士の基準のほうが高くなることが分かります。
(4)死亡慰謝料
被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料は次の2種類があります。
イ 死亡者本人の精神的苦痛に対して支払われるもの
ロ 残された遺族の精神的苦痛に対して支払われるもの
このうち、イを請求する権利は死亡者本人にありますが、死亡により遺族に相続されるため、通常はイ・ロともに遺族が請求することになります。
死亡に至るまでに入通院した場合、死亡慰謝料とは別に1の入通院慰謝料も請求可能です。
【自賠責の基準の場合】
自賠責の基準では、
死亡した本人の死亡慰謝料は400万円です。
これに加え、遺族の慰謝料は次のとおりです。
- 遺族が1名の場合:550万円
- 遺族が2名の場合:650万円
- 遺族が3名以上の場合:750万円
- 死亡した本人から扶養されていた者がいる場合:+200万円
なお、ここにいう「遺族」とは、原則として死亡者本人の父母・配偶者・子に限られます(民法第711条)。
【弁護士の基準の場合】
これに対し、弁護士の基準では、死亡した本人の死亡慰謝料と遺族の慰謝料を合算して支払われます。
金額は、死亡した本人の家族内における立場によって変わります。
具体的には、死亡したのが
- 一家の大黒柱の場合:2800万円
- 母親、配偶者の場合:2500万円
- その他の場合:2000万~2500万円
となります。これらを基準にし、個別の事由を考慮して金額が増減されます。
【自賠責の基準と弁護士の基準の比較】
例えば、サラリーマンの父親と専業主婦の母親、小中学生の子ども2人の家庭で、母親が交通事故により死亡した場合の死亡慰謝料額(目安)は、
- 自賠責の基準の場合:1150万円
- 弁護士の基準の場合:2500万円
となります。
やはり、弁護士の基準のほうが一般的には金額が高くなります。
弁護士に追突事故の示談金交渉を依頼すると、請求できる金額が増額できる可能性がある
交通事故の加害者に対して賠償金を請求する場合、その内容や金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。
被害者が自分自身で(または加入している保険会社の示談代行サービスにより)示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準に基づく低い金額を提示してくることが通常です。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合、最も金額の大きい基準(通常は弁護士の基準)が用いられます。
これにより、加害者側が提示してくる慰謝料を増額できる可能性が高まります。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットはここにあります。
任意保険の弁護士費用特約を利用できることがある
もっとも、示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかるというデメリットがあります。
しかし、自身で交渉すると、弁護士の基準で保険会社が交渉に応じてくれる可能性は低いです。
そのため、弁護士費用がかかることを考慮したとしても、弁護士に依頼した方が、自身で交渉するよりも多くのお金を手に入れることができるケースもあります。
また、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、「弁護士費用特約」が利用できることがあります。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」は自身が任意保険に加入している場合だけ利用できるのではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害事故に遭った車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
【まとめ】追突事故の慰謝料請求でお悩みの場合はアディーレ法律事務所にご相談ください
交通事故で加害者に請求できる賠償金にはさまざまなものがありますが、慰謝料については、専業主婦(夫)という立場が金額の算出に影響することはありません。
また、弁護士が示談金交渉に入ることで、加害者側の保険会社が提示する慰謝料額を増額できる可能性があります。
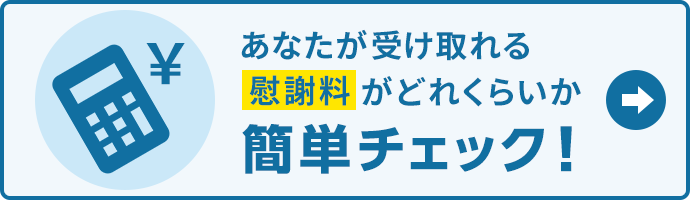
追突事故の慰謝料請求でお悩みの場合は、アディーレ法律事務所に相談ください。
アディーレでは、富山県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
富山にお住まいの方で、交通事故の賠償請求をしたいならアディーレにご相談ください。
【対応エリア】富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市など




弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。